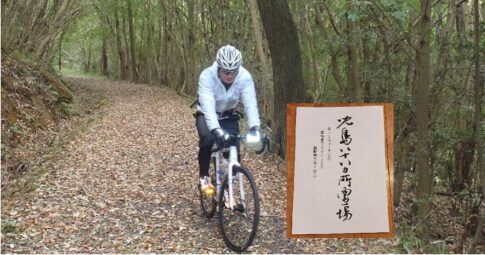私は今年で52歳になりますが、50歳前後から、非常に疲れやすくなりました。
47~48歳頃までは、二日続けて激しいトレーニングをしても、一晩寝たら回復できていたのですが、今では、二日続けてトレーニングすることができません。
特に今年は、花粉症の悪化に伴って、慢性的な疲労感と倦怠感が続いています。
疲労が蓄積すると、トレーニングだけでなく、著書の執筆活動にも影響します。
そこで今回は、疲労感と倦怠感を解消する方法について考えてみました。
目次
疲れの原因は明らかにオーバーワーク

私の場合、疲れの原因として思い当たるのはただ一つ…、オーバーワーク(過労)です。
私は仕事中、ほとんど座ることがありません。
毎日50~60人の患者さんに対応するため、常に身体を動かし続けているといっても過言ではありません。
そして仕事が終わった後は、少しくらいの疲労感、倦怠感があっても無視してトレーニングします。
私は自分のトレーニングをすべて記録していますが、それによると、三日間続けてトレーニングしなかったのは、昨年の11月25日にハーフマラソン大会に出場した後の三日間だけです。
それ以外は、三日続けてトレーニングを休んだことはありません。
これでは、慢性的にオーバーワークになるのは当然です。
そこで今回は火曜日に筋トレして、水曜・木曜・金曜の三日間はトレーニングをしませんでした。約半年ぶりのことです。
おかげで土曜は体調が万全で、問題なくトレーニングすることができました。
休養しても回復しないなら、何かの病気かも…?
例えば休日は寝坊して一日中ダラダラと過ごす、脂っこい食事、アルコール、間食は避けて胃腸を休ませる…。
このようにして十分な休養をとれば、オーバーワークが原因の疲労ならば、確実に回復できるはずです。
ところが何らかの病気が疲労に関係している場合は、そうはいきません。
疲労感や倦怠感は、すでに何らかの病気が悪化していることを知らせるアラームの可能性もあるからです。
放置しておくと、それらの病気を進行させてしまうおそれがあります。
疲労感を伴う病気としては、風邪、肥満・高血圧・糖尿病・高脂血症・高尿酸血症(痛風)といった生活習慣病の悪化、貧血、がん、肝臓や腎臓の機能低下などさまざまです。
十分に休養したにもかかわらず、疲労感・倦怠感が消失しない場合は、思い切って病院で検査してもらうことが大切です。
多くの病気は血液検査や尿検査でチェックすることができます。
心と身体を酷使し続けていると、精神病や突然死(心筋梗塞、脳梗塞)に見舞われる危険性もあるので、十分な注意が必要です。
長引く疲労感は四つの疲れの連鎖である
疲労は大きく4つに分けることができます。
「内臓の疲れ」「自律神経の疲れ」「精神的な疲れ」「筋肉の疲れ」です。これら四つが影響し合い、慢性的な疲れを引き起こしています。
内臓の疲れ
脂っこい食事や、過食、アルコールなどは、大きな負担となって胃や腸だけでなく、肝臓、腎臓、膵臓などの内臓を疲労させます。
こんな自覚症状が増えてきたら要注意!!
[内臓の疲れ]
□便秘がちである □よく下痢をする □食後に胃がもたれる
□肌荒れや吹き出物がある □ときどき胃がムカムカする
□急に胃が痛くなることがある。
精神的な疲れ
人間関係、仕事のプレッシャー、心配事、悩み、不安などは、精神を疲れさせます。一人で気ままに生きることなどできませんから、人は誰でも精神的な疲れが必ずあります。
こんな自覚症状が増えてきたら要注意!!
[精神的な疲れ]
□ささいなことでイライラする □最近ワクワクすることがない
□やる気がでない □すぐに後悔する □一つのことに集中できない
自律神経の疲れ
自律神経とは、内臓などの活動を調整している神経で、「交感神経」と「副交感神経」があります。自分の意志で筋肉を動かせる運動神経とは異なり、自分の意志でコントロールが困難な神経です。
不規則な生活、肉体的、精神的な疲労は自律神経を乱れさせ、その結果、身体にさまざまな不調が現われます。
こんな自覚症状が増えてきたら要注意!!
[自律神経の疲れ]
□なかなか寝つけない □朝は食欲がない □風邪の症状がでやすい
□排便の時間が不規則 □急に体がほてったり冷えたりする
筋肉の疲れ
身体を酷使した後は、筋肉に疲労が残ります。筋肉疲労のほとんどは使い過ぎが原因ですが、ケアを怠ると慢性的な筋肉のコリ、靭帯や腱の損傷といった障害を負うことがあります。
こんな自覚症状が増えてきたら要注意!!
[身体の疲れ]
□身体がだるい □目が疲れる □肩がこる
疲労から回復するための生活習慣とは?
質のよい睡眠
何はともあれ、十分な睡眠をとることが一番です。
睡眠不足は免疫機能を低下させるので、風邪をひきやすくなり、どんどんと悪循環に陥ってしまいます。
私の場合、今年は花粉症がひどく、寝ている間に鼻閉で息苦しくなり、目が覚めることがしばしばありました。
熟睡できていないため、翌日も身体がダルくて仕方ありません。
十分な睡眠を確保するため、病院で処方してもらったアレルギーを抑える薬を服用しました。
薬をあまり飲みたがらない人もいますが、睡眠の質を確保するためには、意固地にならず薬を飲んで楽になるのが良いと思います。
休憩時間には必ず仮眠する
疲れているからといって、そう簡単に仕事を休むことはできません。
仕事のパフォーマンスを維持するためには、休憩時間に少しでも仮眠するようにしましょう。
わずか20分程度の仮眠でも、日中の疲労回復には絶大な効果があります。
関連記事→【パワーナップが凄い! 仕事中にとるチョッとした睡眠】
胃腸に負担をかけない食事
疲労により内臓機能も低下します。疲れているからといって高栄養のものをたくさんたべるのは控えたほうがよいでしょう。
特に食べ過ぎると消化に時間がかかります。
消化の良い、自然なもの、例えば野菜や果物、ヨーグルトなど消化のよい自然な食べ物で内臓をいたわりましょう。
身体を動かすことで全身の血行を促進
私の場合は、日中はバタバタと動きっぱなしで、仕事後もトレーニングで肉体を酷使します。そのため仕事後や休日は、安静を心がけています。
しかし仕事で長時間同じ姿勢を続けている人、運動習慣のない人は、全身の血流が悪くなりがちです。
精神的には疲れていても、肉体的にはそれほど疲労していない場合、そのアンバランスで十分な睡眠がとれない場合があります。
ですから1日30分ほど、意識して歩く、階段を上るなどして肉体を疲労させることも大切です。
何はともあれ「無理は禁物」
肉体も精神も、鍛えなければ強くなりません。
しかし鍛え過ぎて疲労が蓄積し、心と身体を病んでは意味がありません。
己の限界に挑戦しつつ、健康体を維持する。
そのためには自分の心と身体が発するシグナルを吟味し、時には思いっきりダラダラして休養することも必要です。
十分に休養して心と身体をしっかりと回復させてやった後は、さらに充実したトレーニングができます。
くれぐれも疲労が蓄積した状態で無理することは禁物です。